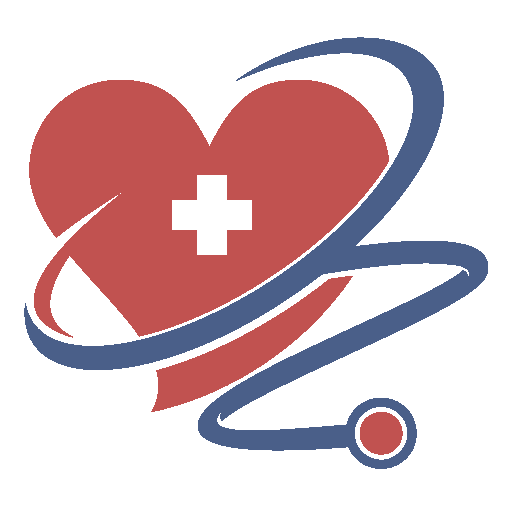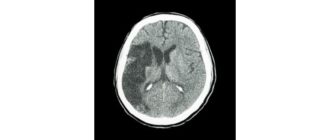誤って塩分が多すぎると認知機能障害を引き起こす可能性があると、幸運にもこの雑誌に掲載されている新しい研究によれば、これらの悪影響は逆転する可能性があり、

私たちの食生活で食塩が多すぎると、心血管疾患や高血圧のリスクが高くなることはよく知られています。
しかし、脳血管疾患、脳卒中、認知障害などの脳関連の問題はすべて食塩に関連していることはあまり知られていません。
新しい研究の著者が説明するように、これらの負の作用の背後にある可能性のあるメカニズムの1つは、脳血管内のいわゆる内皮細胞を含むことが示唆された。
内皮細胞は血管を覆っており、血管緊張を調節する役割を担っていますが、食塩摂取量が多いとこれらの細胞の機能不全に関連しています。
上皮機能不全が慢性疾患の過多をもたらすことが知られているが、塩誘導性内皮機能不全がいかにして長期間に亘って脳に影響を及ぼすかは不明である。
これは、ニューヨーク州ニューヨークのWeill Cornell MedicineのCostantino Iadecolaによる研究努力の主導者であった研究者を説明しながら、脳が安定して円滑に機能する酸素の流れに大きく依存していることを考えると、特に重要です。
彼らの論文では、Iadecolaらは、過剰な食塩が腸、免疫系、そして最終的には脳にどのように影響するかを示しています。
どのように過剰な塩が腸の脳の軸に影響するか
Iadecolaとチームは、12週間の間、塩分が多いヒト飼料と同等のマウス群を飼育した。
最初の数週間後、内皮機能障害ならびに脳への血流の減少がマウスにおいて認められた。さらに、行動試験は、げっ歯類における認知低下を明らかにした。
しかし、彼らの血圧は変わっていない。
重要な発見は、腸のいわゆるTH17白血球の増加であった。次に、多数のTH17細胞が、血漿インターロイキン-17(IL-17)と呼ばれる炎症誘発性分子のレベルの上昇をもたらした。
研究者らはまた、血液中の高レベルのIL-17が負の認知および脳血管の影響をもたらす分子経路を同定することができた。
研究者は、その発見がヒト細胞で複製するかどうかを知りたがっていました。そこで、彼らはヒト内皮細胞をIL-17で処理し、同様の結果を得た。
Iadecolaとその同僚が説明するように、
「この知見は、ダイエットに関連する環境要因が腸内の適応免疫応答を導き、神経血管調節不全および認知障害を促進する腸管の軸を明らかにする」
食生活の変化は、
良いニュースは、高塩食の悪影響が可逆的であるように見えることです。マウスは12週間後に正常な食餌に戻され、結果は奨励的であった。
「高塩食の有害な影響は、マウスを正常な食事に戻して、血管機能障害および認知障害の可逆性を指し示すことによって廃止された」と著者らは書いている。
さらに、彼らはまた、過剰な塩の影響を逆転させた薬を試しました。アミノ酸L-アルギニンは、正常な食餌に戻すのと同じ効果をマウスに与えた。
この調査結果は、生活習慣の変化や新しい種類の薬剤が、高塩食の負の影響を相殺するのに役立つ可能性があることを示唆しています。